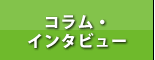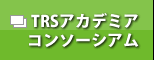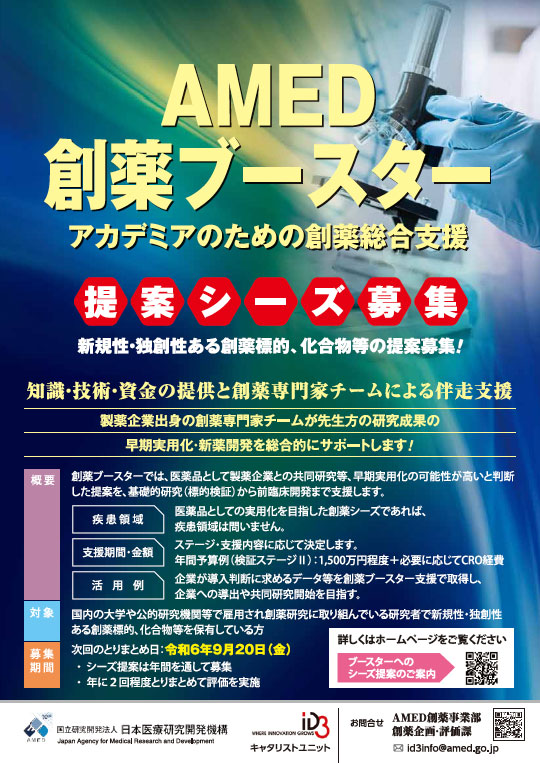コラム
2024年2月に行ったシンポジウムでの講演をベースにコラムを作成していただきました。
アカデミア研究の実用化に向けて
私が在籍している![]() 新生キャピタルパートナーズは、新生銀行からスピンオフする形でライフサイエンスに特化してベンチャー投資を行うベンチャーキャピタル(VC)です。そのため、創薬研究の目利きや臨床開発の知見を持ったメンバーが揃っています。本日はライフサイエンスに投資を行っている立場から、創薬の現状をご説明した後に、アカデミア研究を実用化するために必要なこと、ベンチャーを設立するための視点等をご説明したいと思います。
新生キャピタルパートナーズは、新生銀行からスピンオフする形でライフサイエンスに特化してベンチャー投資を行うベンチャーキャピタル(VC)です。そのため、創薬研究の目利きや臨床開発の知見を持ったメンバーが揃っています。本日はライフサイエンスに投資を行っている立場から、創薬の現状をご説明した後に、アカデミア研究を実用化するために必要なこと、ベンチャーを設立するための視点等をご説明したいと思います。
製薬会社の研究開発の効率は、年々低下しています。1950年には1千億円の研究開発費があれば60〜70の新薬ができていました。一方、現在では、新規ターゲットの枯渇が進み、難しい技術を使わないと新薬が作れなくなってきたということもあり、1千億円の研究開発費があっても1つの新薬が作れるかどうかであり、もはや開発した医薬品がブロックバスターにならないと採算が取れなくなってきています。そんな中、医薬品開発の主戦場は製薬会社から大学・バイオベンチャーに移ってきており、上市される医薬品の約2/3程度はアカデミアやバイオベンチャーが起源です。
近年、中国やインドの研究者が台頭してきているとはいえ、日本の科学技術のレベルはいまだ高く、世界でもトップ5〜10に入る科学技術大国です。そのため、日本には非常に優れた研究が至る所にありますし、人口当たりの研究者数も多いと言われています。一方で、研究を実用化して形にするところが非常に弱いところが欠点でもあります。その理由の一つが資金力です。例えば、アメリカおよび日本の研究グループがそれぞれ同時期に優れた技術を発見しベンチャーを設立した場合、日本ではシード時の資金調達として2〜3億円しか集まらないのに対し、アメリカでは100〜150億円を集めて一気に医薬品開発を進めることが可能です。
アカデミアの研究を実用化するには、バイオベンチャーを設立するか、もしくは、製薬会社と共同研究をするか、の2つの方法があります。これまで日本では後者、すなわち製薬会社との共同研究により医薬品になるものが主流でしたが、世界的に見ると、バイオベンチャーによって創られる医薬品がほとんどです。この2つの方法の違いは以下の通りです。共同研究では、製薬会社主導で開発が進む一方で彼らの最先端のインフラや長年のノウハウを使えますし、製薬会社の資金で医薬品を開発することができます。対して、バイオベンチャーを設立する場合には自身で開発戦略を立てて進むため手作り感がありますが、資金的には厳しいため、コンパクトにスピード感をもって研究開発を行っていく必要があります。共同研究においては、製薬会社の研究開発は石橋を叩いて進むために、動物実験で良い結果が出ないとそこでストップしてしまいますが、ベンチャーではリスクを取って進むことができるため、動物実験で必ずしも全ての項目をクリアしていなくても先に進めるケースが多々あります。一方、資金的な観点で言えば、大規模な臨床試験が必要となるような疾患については、日本のベンチャーの体力では臨床試験を実施することが難しく、製薬会社との共同研究で進めた方が良いものもあります。最後に、成功した時の経済的利益については、共同研究よりもベンチャーの方が大きな対価を得られるケースが多いです。実際にどちらかを選ぶ場合には、これらの点を考慮しながらより良い方法を選ぶことが必要になります。
今やベンチャーを始めること、ベンチャーで働くことは異端の選択でもありませんし、リスクも大きくありません。一方で、ベンチャーは大手企業とは組織も文化も資金力も仕事のやり方も異なります。製薬企業とは違い、医薬品を開発してもMRを持たないため自販することができませんし、自社で行えることができる研究開発や使える資金など様々な制約が存在します。そのため、初めてバイオベンチャーを立ち上げる場合、多くの方が同じような壁にぶつかり、同じようなことが分からず、苦労しています。米国ではなぜ起業が多いかというと、シリアルアントレプレナー(連続起業家)が多く、そのような失敗するポイントに対してアドバイスを受けやすいことや、起業した後のイメージについて共有が進んでいるためです。日本では失敗に対する危惧で起業できない方が多いかと思いますが、機会を見つけて経営者やベンチャー起業家のお話を聞いていただくのが良いかと思いますし、彼らがどんなところでつまずいたのか失敗事例を学ぶことがとても重要です。また、仮に一度失敗をしたとしてもそれが次の成功につながるかもしれません。私たちも一度バイオベンチャーでうまくいかなかった方を積極的に採用しています。失敗のポイントを知っているからです。
大学発ベンチャーはこの10年で2倍以上、1年で400社ぐらい増えています。すなわち1日1社以上のベンチャーが生まれていることになります。そして、今はベンチャーの立ち上げには非常に良いタイミングだと思っています。前述した通り、創薬の主戦場は製薬会社からアカデミアやベンチャーに移ってきています。製薬会社の研究者がベンチャーやVCに流出し、優秀な人材がコンサルタントとしてサポートしている例も増えています。ベンチャーが入居できるような研究施設やシリアルアントレプレナーのような方々も増えているように思います。
ご存じの通り、創薬は基礎研究を経て動物実験、非臨床試験、臨床試験、承認申請へと進みます。アカデミアで行う研究はその前にあるわけで、そこから基礎研究・非臨床へと進むにはかなりの時間がかかります。京大本庶先生および小野薬品によるおよびオプジーボの開発の例では、最初に本庶先生より標的となるPD-1に関する論文が出たのは1992年です。その時点では、PD-1という標的を狙うことでどのような疾患を治療することができるか、そのポテンシャルについてはまだ不透明でした。本庶先生はPD-1ががん治療のための標的となり得ることを見つけるのに実に6年の年月を費やし、1998年になってようやく免疫との関連性を調べた論文を発表しています。そしてオプジーボのもととなる特許出願が行われたのが2002年ですが、もしバイオベンチャーを設立するとしたら、この特許出願をした2002年の時点になるでしょう。そして、2008年に第1相臨床試験を開始し、2014年に承認に至っています。バイオベンチャーであれば、第2相臨床試験が終わったあたりで製薬会社にライセンスをするか、もしくは開発資金を自社で拠出することが難しければ第1相臨床試験時に製薬会社に導出をして、PoCが取れたあたりで上場を目指します。つまり、ベンチャーを2002年に立ち上げて、 PoCが取れた2010年〜2012年あたりに上場ないしは売却するということになります。
資金調達はバイオベンチャーの研究開発ステップに合わせて、数回に分けて行われます。多くの場合、非臨床試験が始まる時、臨床試験に入る時にそれをマイルストンとして資金調達をし、PoC取得後に上場するのが一般的な流れです。バイオベンチャーの平均を取ると、だいたい設立してから上場まで7年ぐらいかかっていますが、7年というのが重要で、私たちのようなVCファンドには10年間というファンド期間があり、その期間内にVCファンドに資金を拠出してくれた投資家にお金を返却しなくてはなりません。そのため、どんなに長くても投資時点から10年以内には上場できるような計画でないと投資はできない、ということになります。
ベンチャーへの投資額を日米で比較すると、ライフサイエンスに限った場合、日本は米国の約100分の1です。バイオベンチャーの最終的なゴールは薬が患者さんに届くことですが、上場することも一旦の区切りとなります。米国Nasdaq市場では、年間7〜80社のバイオベンチャーが上場している一方で、日本では毎年3〜4社のバイオベンチャーしか上場できないのが現実です。
前述の通り、アカデミアにおける研究成果を医薬品にするためには、バイオベンチャーを設立するか、製薬企業などと共同研究をする必要があります。バイオベンチャーを設立する場合でも共同研究を行う場合でも、最終的な医薬品を製造販売するのは製薬会社ですので、製薬会社に好まれるような研究テーマでないとゴールまで辿り着けません。私たちVCの評価ポイントに関しても、製薬会社にライセンスする、もしくは売却することができるかどうかという観点で評価を行います。また、研究シーズの特許が強固でないとベンチャーを作っても資金調達ができませんし、その後、製薬企業へのライセンスもできません。そのため、特許には可能な限りお金をかけても構わないと言えます。可能であればライフサイエンスに専門性のある弁理士事務所に依頼を行い、強固な特許出願を行うことが良いです。多くの場合、その特許はアカデミアが保有することになりますが、ベンチャーを設立する際に問題となるのが、その特許をベンチャーに移すことができるのか、どんな条件で移せるのかということです。大学により規定や考え方が違うので、ベンチャーを設立するのであれば、なるべく早期から大学と話をしておくのが良いと思います。他の事例も参照し、ベンチャーにとって好ましい状況を作るように交渉するのも大切です。
バイオベンチャーの場合は、上市にたどり着くまでの開発リスクをいかに小さくするかが課題となります。統計学上、第1相から承認まで至る開発成功確率は12.5%しかありません。私たちも資金を出す立場から、この確率をできるだけ上げたいと考えています。一般的に言えるのは、資金がないベンチャーの場合、できるだけコンパクトな治験で承認を取ることが可能な希少疾患を選んだり、既に診断基準が明確な疾患を選ぶだけでも、成功確率が上がります。疾患のみならず、モダリティ、バイオマーカーの有無などでも成功確率はだいぶ変わりますので、もし疾患を自由に選ぶことができるのであれば、上記のようなことを念頭に置き、なるべく開発成功確率が高い疾患を選ぶことも大切です。
ベンチャー設立後のビジネスモデルは、パイプライン型かプラットフォーム方か、つまり、医薬品を開発するか、持っている技術を使って製薬会社と提携し、彼らが欲しいプログラムを作るか、という2つに分かれます。どちらがいいということはありませんが、プラットフォーム型の場合、1つ1つのプロジェクトだけでは収益が上場するのに不十分なことも多く、近年は上場のハードルが上がりつつあります。
多くの先生からよく質問を受ける点を2-3説明します。まず、ドラッグリポジショニングの可能性については、患者さんのために新しい薬を創りたいという使命のために開発を行うのであれば進めていただいて問題ありませんが、ベンチャーを成功させたいという観点から言うと、特許がない化合物の場合には製薬会社にライセンスしにくいという問題があります。そのため、剤型を変えたり用途特許を取るなど何らかの工夫が必要になります。次に、研究者が自分でベンチャーの社長になるべきかどうか、という点です。個人的には、研究者はアカデミアの研究に専念し、ベンチャー経営は経営者に任せるべきだと考えています。社長人材の確保が難しいような場合には我々VCに相談頂くことも可能ですし、VCのキャピタリストが社長を務めるというケースもあります。社長の件のみならず、ベンチャーの設立においては、資金調達など多くの点を考慮する必要があります。これらを全て自分で解決することは困難です。そのため、ベンチャー設立を検討するのであれば、設立前からVCに資金の相談をするケースも増えてきていますし、カンパニークリエーションと言って、アカデミアの先生とVCが共同でベンチャーを設立するケースも増えています。モデルナも米国でこのカンパニークリエーションによって設立されたベンチャーです。
新生キャピタルパートナーズ株式会社 パートナー※
栗原 哲也
※2024年2月22日講演時のご所属です。