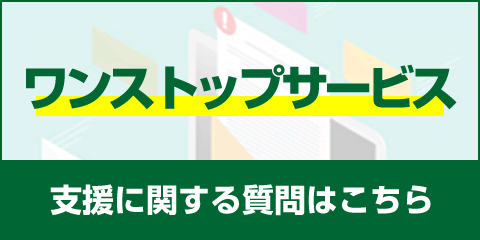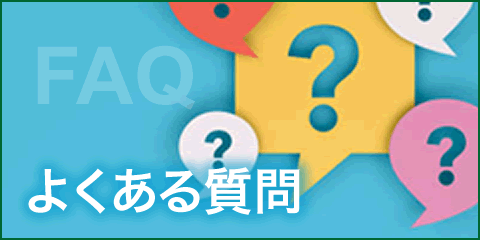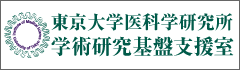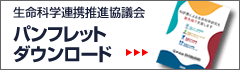第15回国際ゲノム会議(15AGW)に参加して
金井 昭教、鈴木 穣(東京大学 大学院新領域創成科学研究科)
会議概要
第15回国際ゲノム会議が2025年7月2日から4日までの3日間、一橋講堂(学術総合センター)にて開催された。本会議には先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム(PAGS)も共同スポンサーとして参画した。
近年のゲノム解析技術は加速度的に進展しており、シークエンサーを用いたゲノム解析に加えて、シングルセル解析やマルチオミックス解析プラットフォームの発展、さらにそれらから得られる膨大なデータを解析する情報解析技術やAI技術の進化などが注目されている。本会議はこうした最先端の技術と知見を研究者およびバイオ関連企業から直接聞くことのできる機会である。会議は2年に1度開催されており、前回は2023年秋に開催され、今回は夏の開催となった。今年は「Genome, Cell and Disease」をテーマに、最新のゲノム・オミックス解析技術発展が紹介され、国際的なトップサイエンティストがスピーカーとして招かれた。
1日目(7月2日)
最初のセッション1「Human Pangenome」では、前回の会議で紹介されたヒトゲノム完全配列(T2T genome)からPangenomeへとテーマが移行した。Human Pangenome Reference Consortiumの取り組みをはじめ、ロングリードシークエンスを用いたがんの構造変異解析やセントロメア領域の解析に関する発表が行われた。
続いて、Núria López-Bigas博士(Institute for Research in Biomedicine, Barcelona / Pompeu Fabra University)による基調講演が行われた。がんおよび正常組織における体細胞変異についての研究が紹介され、ドライバー遺伝子に基づいたがんの個別化治療を目指し、標準治療と遺伝子変異に関する網羅的な解析について議論が交わされた。
セッション2「Large-scale Genome」では、国際的なバイオバンクデータを使用したゲノムワイド関連解析(GWAS)、発現量関連遺伝子座(eQTL)解析、ポリジェニックリスクスコア(PRS)解析を通じて複雑な形質や疾患の理解、さらには個別化医療への応用に向けた最新の研究成果が報告された。
2日目(7月3日)
セッション3「Digital pathology」では、病理スライド画像から個別化医療を実現するためのAIモデルの構築、AIと病理画像を組み合わせたがんの層別化、さらに病理画像と空間解析を統合したがん研究に関する発表が行われた。
「Plenary Talk」セッションでは、Dan Landau博士(Weill Cornell / New York Genome Center)が登壇。血液がんのクローン進化をシングルセル解析に基づいて系統樹として再構築し、腫瘍の理解および治療への応用について講演が行われた。
セッション4「Disease」では、B細胞リンパ腫の腫瘍微小環境の解明、血液細胞における老化とがんの関連、脳腫瘍におけるモザイク変異の解析、心不全における空間オミックス解析など、多様な疾患に関する先端研究が紹介された。
3日目(7月4日)
セッション5「Multiomics in disease / New Frontiers in disease genomics」では、肝臓がんにおけるがん胎児性の解明、がん免疫療法耐性に関わる腫瘍浸潤性リンパ球についての研究、スプライシングを標的としたがん治療の新展開について発表が行われた。
PAGSとの共同セッション「Technology Innovations and Beyond」では、最新の空間トランスクリプトーム解析、シングルセル解析、長鎖・短鎖型シークエンサーのアップデート、またそれらの技術を活用した最先端のマイクロバイオーム、感染症、血液がん研究の最前線について、活発な議論が交わされた。
最終セッションとなるセッション6「AI / Computational Biology」では、AIを用いたゲノムアセンブリおよび解析、哺乳類発生過程における細胞系譜の高解像解析、計算科学的手法による高解像度オミックスからのシステムの理解に関する研究成果が発表された。
会議のまとめ
15AGWはゲノム、病気・医療、それらを理解するためのシークエンシング技術、シングルセル解析、空間オミックス、計算科学、AIなど、多岐にわたる最先端のテーマが集結した非常に有意義なシンポジウムであった。前回、2年前以降の空間オミックス解析分野における著しい進展を受けて、「Digital pathology」という新たなセッションが設けられたことは興味深い。加えてAIによる解析技術の発展も目覚ましく、今後の研究に大きなインパクトを与えることが期待される。シークエンサーにおいては精度の向上とコストの低下がさらに進み、シングルセル解析も大規模化と低コスト化が進展している。空間オミックスに関しては高解像度化が進み、これらの最新動向がゲノム研究者の間でも広く共有された。
また、会期中には25題のポスター発表も行われ、研究者同士の活発な議論がなされていた。ポスター会場と同じホール内に企業による展示ブースも設置され、研究者と企業との最新テクノロジーに関する情報交換や相談も積極的になされていた。
筆者も3日目のランチョンセミナーでの演者および「Technology Presentation」のコーディネーターとして本会議に参加し、大変貴重な経験を得ることができた。